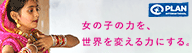不快で不愉快な言葉は孤独と常に隣り合わせ
発する言葉に責任を取らせない
人に不幸を呼び込み
自分までも巻き込まれる
言葉を謙虚に使う事
たとえ辛くとも
熟した言葉を紡ぐなら
やがて引きずられるように心がついてくる
口から出るその言葉
時として助けにもなるが
災いにもなる
言葉に意識を乗せて
注意深く
丁重に
言葉は、あなたの精神状態を表しています。
見方を変えれば、言葉を大切にする事で、心も穏やかに出来るのです。
普段、日本に住んでいるので、日本語を使うのが当たり前だ。
小さい時から、コミュニケーションの道具として言葉は、大切な役割を担っている。
子供達が言葉を覚えていく過程で、影響を与えるのは傍にいる親や大人。
常に、言葉遣いに気を付けながら、子供と接する事はなかな難しいが、子供は真似ながら覚えていくもので、知らず知らずのうちに、親の話し言葉を真似て話す。
私の住む3階建てのハイツの住民には、フィリピン人が多く住んでいる。
フィリピン人夫婦や私の様な国際結婚の夫婦、日本人と離婚した人、離婚して一人親で子供と住んでいる人など、色々なバックグラウンドがある人達。
外国人がなかなか賃貸出来ない中、このハイツの大家さんは、裏にある建設会社の社長でフィリピン人に対し、非常に親しみを持って接してくれるお陰で、口コミでどんどん増えたというのが現状だ。

私がフィリピンパブに通い出した頃、彼女達が話す言葉は、現地語のタガログ語と英語。
当時は、日本語をほとんど話せない、若い女性で溢れかえっていた。
2度3度と来日している女性は、ある程度日本語が話せるようになるのが、その覚えた言葉は、接している日本人男性ばかりという事もありハッキリ言って汚いのだ。
「バカ」「ふざけんな」そんな言葉をたくさん聞くからでしょう。
私も、彼女達から聞くタガログ語で覚えたのは、「ふざけんな」「なんだよ、てめえ」「浮気者」といった内容の言葉ばかり。
面白い言葉があってタガログ語の「バカ」は「牛」の事で「バブイ」は「豚」の事です。
「レイチェ」とは「こいつ何言ってんだよ!」的なニュアンス。
ほら覚えたでしょう?!
勿論、英語も同じような汚い言葉をよく聞いていた。
外国語の入り口って、案外そんなものなのかもしれない。(あくまで実践としての話し言葉ですが)
そのハイツには、私の子供と同じようにハーフの子供もいるが、言葉遣いがあまり良くない。
そう、親の言葉が悪いからなのです。
勿論、親の責任をどうのこうのと言うつもりではない。
前述のようにフィリピン人たちが親となっても、汚い日本語ばかり聞かされて暮らしていた影響が大きいからだ。
残念な事にフィリピンだけでなくハーフの子供や、外国人同士の夫婦の子供達が不良になる事は珍しくない事で、差別や疎外感、日本語、特に漢字の学校からの書類を読めない親に見せないで捨ててしまう事もしょちゅうある。

子供は、日本語がうまく話せない、書けない親をバカにするようになり、余計に親とのコミュニケーションが少なくなってしまい、結果良くない友達とつるむようになってしまうのだ。
言葉が、どれほど大切かを表すような事例だが、日本に住む外国人達にとっては、見た目以上に苦労しているのだ。
振り返って私達日本人はどうだろうか?
昔に比べて、SNSで用を済ます事も多くなっている。
近所付き合いも希薄になり、誰とも話さない、独居老人や一人暮らしの若者も増えている。
また、テレワークやリモートでは、生身のチョットした顔や仕草が見づらくダイレクトに相手に言葉が伝わる。
画面から人柄や雰囲気伝わりにくいからでしょう。
ますます、言葉選び、言葉遣いに注意しなくてはいけない世の中になっていくだろう。
たまたま、自転車屋さんにチューブを買いにいった時、小さな子供連れのお父さんが店員に話しかけているのを聞いたのだが、「子供の自転車のハンドルがまっすぐではなく、曲がっているから直して欲しい」という内容だった。
前輪を股に挟んでひねればすぐ直る簡単な事だが、たぶん工具も無く、知識も無かったのだろう。
私は自転車のパンク修理やメンテナンスによく工具を使う。
道具箱の中にはそれなりの工具がそろっているので修理もはかどる。
もし工具がそろっていなければ時間もかかるし、先ほどのお父さんの様に、人に頼む事に結局なるかもしれない。
面倒くさい、汚れたくないという事は別として、持っているモノ(この場合工具ですが)があればあるほど、行動範囲も幅も広がりる。
それは、言葉にも言える事で、沢山の言葉、言い回しや種類が多いほど豊かな表現が出来る事を意味する。
先人たちが生み出してきた言葉は、受け継がれながら洗練されていったからだ。
折角、残してくれた知恵が隠れている言葉を学ぶ、知る事は、決して無駄では無い。
また言葉を発する時には、そのトーンや大きさ、表情も味付けのように働き、豊かであればあるほど、しみ込んでくる。
世界には、複雑な習得する難易度が高い言葉が沢山ある。
その国の自然や自然相手の農林水産といった生業(なりわい)、風習など様々な条件が言葉を生み出している為、それに合わせて必要な表現が生まれ、正に国の歴史そのもとも言える。
だから、言葉を理解する事は国を理解する事なのだ。
最近よく使われるグローバル化という意味は、自分の事、育った国の事、使う言葉を丁寧になぞり、発信できてこそグローバル化だは無いだろうか。
日本人ならば誰もが難なく書き、話せる言語の難易度がトップクラスの日本語。
今一度、原点に返り見直しても良いのではないだろうか。
言葉は、敵から逃れる為や、季節を感じ多彩に表現する事で農作物を守る為や、育てる知恵として機能してきた。
勿論支え合い、無駄な争いを避け仲良く暮らす為に。
そんな歴史が、日常的によく使う言葉の中に隠れているのだ。
それは、一人では生きていけない人間としての、集団の中で必要不可欠だったからだ。
誰かを傷つける為、不快にしたり落ち込ませたりする為に生まれたものでは決して無い。
集団の中で生きる為の知恵を、そんなことに使う事自体が間違っている。
命を奪う暴力や力に頼る事無く、歩み寄りや和解する為の道具でもあったのだ。

上手く話せない、話題が無い、思っている事の半分も伝わらない、そんな事は問題では無い。
大切な人に語る時も、見知らぬ人に語る時も、心の広さが全てなのだ。
それには、沢山の人との分け隔て無い出会いと経験や失敗、涙や汗が必要不可欠であり、そして何より、聞く耳を持つ事だ。
それが心の中にある言葉の引き出しをどんどん増やし、イザという時にあなたを助けてくれる。
人間関係で必ず必要になってくる言葉は、乾いた心に注がれる水の様な働きを生み出す力を持っている。
いわゆる、沁み通る、染み渡る様に。
このブログでも書いているが、想いは伝えないと意味が無い。
「そんなことぐらい解っているだろう」という勝手な考えは間違っている。
その為に耳があり、口があるのだから。
「私は口下手だ」という人がいるが、余計な事をべらべら話すより、口下手の方がいい事だって沢山ある。
「話す話題が無い」という事もよく聞くが、ちょっとした事を豊かに表現するだけでも、印象はかなり違ってくる。
何もキザな事を話せとは言っていない。
天気の事でも電車から見た風景でも、表現豊かに話せればそれほど多くを語らずとも「人となり」が伝わるものだし、聞き上手になれるチャンスかもしれないのだ。
人生は、生きる事は苦であり、決して楽なモノは無いとこのブログ記事で何度も書いた。
苦であるからこそ、生きたいと願い、幸せになりたいと思うのだ。
人間は、そこに歌を、詩を、芸術や物語を添えて、一時のなかなか味わえない幸せに花を咲かせてきた。
それが、他の動物には無い、人間の力、言葉の力なのだ。
何度も書くが、誰かをおとしめ、傷つけ、ののしる為の道具にするなら、社会は成り立たず自滅するだろう。
そして心の広さ、大きな心とは「包容力」だ。
小さな世界、小さな心の中で生きている中では生まれて来ない力。
周りに流され、学校や職場などの事ばかりに神経を使っている状態も、正に小さな世界と言える。。
私達には「想像力」という素晴らしい力を持っている。
心は自由であり、想像力が世界を広げてくれる。
例え、同じような毎日の繰り返しだとしても心が縛られている訳では無いし、心自体が同じ事を繰り返すわけでも無い。
先人たちの言葉も、現代では色々な形の媒体で知る事が出来き、手助けや導きとして活かせる環境にいる。
本に触れたり、お年寄りと会話したりするのも一つの方法で、それらの素晴らしい沢山の表現力と沢山の豊かな言葉を学ぶ事も世界を広げる手助けになるだろう。

何処の国でも、自国の言葉を大切にしている。
言葉一つで、政権が転覆する事もあるぐらい力がある言葉。
ただ単に伝達だけの手段なら、芸術や音楽は生まれなかったし、味気ない世の中になっていただろう。
季節の移ろいや自然が織りなす様々風景を色々な言葉で表す事が出来るというのは、素晴らしい文化で、同時に心の隅に染み込む様な言葉をかける事も出来る。
人間関係において潤滑剤の様な役割をしているのは誰でも実感するところだし、主語の位置や単語の選び方で、相手の受け止め方も大きく変わってきる。
映画好きな方ならお分かりと思うが、国によって主語の位置(省略しても前後の文脈で解る場合もある)等が違い、当然脳で処理しているので、考え方も見方も違いが生まれる。
その違いがとても大切な事なのだ。
ジャンクフード(栄養価のバランスを著しく欠いた調理済みの食品)ばかり、味付けの濃いものばかり食べていては、コクやうまみ、季節感が感じられなくなるのと同じで、やたらカタカナ英語を使ったり、短絡的な単語ばかり使っていては表現力が低下するばかりか、想いを乗せる事も発する言葉に深みも無くなってしまう。
言葉の貧困は、使っている本人ばかりか、周りの特に子供達にも悪い影響を及ぼす事を頭に入れておかなくてはならない。
何故、繊細な事まで表現できるようになった言葉を私達は獲得したのか?
そして、それを大切にする事の意味を考え直してもいいのではないだろうか?
「ヤバい」「爆上げ」「ダサい」「エモい」等どんどん言葉が生み出されているが、時代に合わせて変化していくという意味で悪い事では無いとは思うが、言葉は芸術といってもおかしくないくらい作者の、すなわち発言者の想いを形にするものという事を知っているか否かで、生き方にも影響する大切なものだと思う。
それは職人やアーティストが使う道具の役割と同じで、私たち自身の道具でもあるからだ。
素敵な言葉は、発した途端映像が浮かんでくるでしょう。
例えば私の好きなノンフィクション作家の吉村昭さん「神々の沈黙」の冒頭部分の抜粋ですが、『1967年十一月下旬、ニューヨーク市の南東部にある庶民の町ブルックリンはすでに冬の気配が濃く、町の中央に立つユダヤ系のマイモニディーズ病院の窓ガラスにも、寒々としたにぶい陽光が反射していた。』
映像が浮かび、何が始まるのか?というワクワク感まで表してる。
勿論、話し言葉では無いが、表現の仕方一つとっても、印象が変わる。
不快だなぁと思う言葉は、まるで角(かど)が多いカタカナやデジタルを想像させるし、心地よい時は、筆で描いた文字の様に、一つのアートを鑑賞しているように思うものだ。

言葉は 時に暴力に 武器にもなる危険な意志を持ち
吐いた途端 自身と共に堕ちていく
残った後ろめたさと後悔は 影の様に張り付いたまま
暗黒の中だけが影の安住の地。
でも
言葉は 時に優しさに 勇気にもなる解き放つ力を持ち
かけた途端 自身と共に支えとなる
あなたが歩き出す後ろで そっと照らし見守る
あなたの幸せをもって その光は薄くなり役目を終える
進化からの贈り物
それが言葉
あなたが発する言葉が、誰かを幸せに出来る。
そんな言葉の力が、今とても必要な時代ではないだろうか?
金子 みすゞ(かねこ みすず)大正時代末期から昭和時代初期の童謡詩人。26歳の若さで亡くなった。
彼女をご存じの方も多いと思うが、私も20数年前に彼女の詩を偶然目にして虜になってしまった。
それから10数年後にちょくちょく話題になりだしたのを覚えている。
彼女が、決して豊かで無かった日々の生活の中で見つけていく、小さな幸せが詩の中に溢れている。
決して幸せと言えない生活の中で、彼女の視点で見る世界は、小さな幸せを積み重ねる事の大切さを浮き彫りにし、また、彼女の想像力の凄さと独特の表現法と相まって、短い詩の世界に無限を感じさせられる事に圧倒される。
ぜひご覧になっていらっしゃらない方は読んでみて欲しい。
↓ あなたの支援で助かる命
「変えたい」気持ちを形にする、 世界最大のオンライン署名プラットフォーム
↓ みんなで社会を動かす仕組み